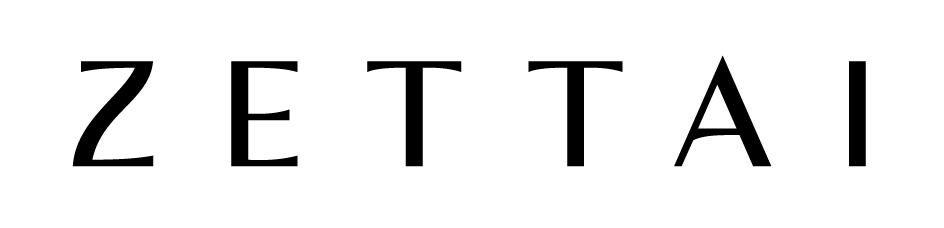アジアのビエンナーレは約25年前から開催数が急増し注⽬が集まり始めた。当時始まった主要なビエンナーレには、光州(1995年)、上海(1996年)、台北(1998年)が含まれる。その後も、釜⼭やシンガポール、広州、横浜、ジョグジャカルタなど、他の都市でもビエンナーレやトリエンナーレが次々と開催された。さらに、シドニー・ビエンナーレのような、グローバル化に合わせて再構成した新しいビエンナーレ・モデルも登場した。そこでは、国際的なアーティストのコレクションを展⽰し、海外出⾝の有名なインディペンデント・キュレーターを採⽤し、テーマとして⾼度に理論的な声明を発表するのが常である。
2000年代初頭までには、アート雑誌業界が新たな「ビエンナーレ化現象」の傾向に警鐘を鳴らすようになっていた。これは、マクドナルドのフランチャイズ店のように、ビエンナーレが地球規模で出現する現象に対する批判であった。⽭盾したことに、ビエンナーレの多くがグローバル化を⾮難するものであったが、ビエンナーレそのものがまさにグローバル化の好例になってしまっていた。また、このようなビエンナーレの急増により、理論的ディスクールは生まれると同時に制度化されてしまうため、急進的で前衛的になりうる可能性を⼀掃するのではないかと危惧された。
あらゆる種類の⾮西洋的パラダイムの生成に関して、少なくとも二つの主要な問題がある。第一に、アジアの地域が⾮常に多様であることは⾔うまでもないが、それ以上に重要でかつ西洋と全く対照的なのは、アジアではいまだに領⼟問題や歴史的な過ちに対する不満がくすぶっている点だ。中国、インド、台湾、⽇本、フィリピン、ベトナム、そしてもちろん朝鮮半島の2カ国は、地域内の⼟地や航海権を巡って今も争いを続けている。またそれら多くの国々において、第二次世界⼤戦や1950年代の朝鮮戦争、台湾対中国、中国対インドの対⽴を含む、様々な戦争はまだ解決されていない。第二の問題は、現代美術を議論するのに必要な理論的なツールは、いまだ西洋、特にフランス、ドイツ、イギリス、アメリカを拠点とする批評家の思想に基づいている点である。欧⽶基準のグローバル理論に基づいた関⼼事と、新しいビエンナーレの参加者の関⼼事を隔てる不⼀致を無視することはできないだろう。

Internacional Errorista, “We are all Errorists” (Taipei Biennial, 2008).
Courtesy of Internacional Errorista and Taipei Fine Arts Museum.
2014年に台北市⽴美術館で協議会が開催された。「アジア・ビエンナーレから新しいパラダイムは⽣まれるか」という協議会の議題⾃体が意味深⻑な問いを提⽰していた。討論者のほとんどが欧⽶の美術評論家であり、多くを語ることはなかった。彼らはアジアの現代美術に無知か、あるいは名ばかりの視察旅⾏に資⾦協⼒した主催の政府に気を遣っただけか、どちらかである。それでもなお、協議会の問いは胸に迫るものがある。ここ数⼗年の間にアジアの現代美術は数々の実践を積み重ね、何かしらの影響⼒を強めてきているようだ。それは⼀体何なのだろうか。グローバル化現象には亀裂が⼊り、西洋のパラダイムが美術鑑賞においていまだ優位性を持つ中、アジアの美術界ではアジア国間の対話とネットワーク構築の重要性が⾼まっている。この現状をデーヴィッド・フレージャーが描いてみせる。

Apichatpong Weerasethakul + Chai Siris, “Sunshower”, 2017. Mixed media.
Installation view: SUNSHOWER: Contemporary Art from Southeast Asia 1980s to Now,
The National Art Center, Tokyo / Mori Art Museum, 2017.
Photo: Kioku Keizo.
Photo courtesy: Mori Art Museum.
Installation view: SUNSHOWER: Contemporary Art from Southeast Asia 1980s to Now,
The National Art Center, Tokyo / Mori Art Museum, 2017.
Photo: Kioku Keizo.
Photo courtesy: Mori Art Museum.
この理論的な乖離に関する、痛烈な例は2008年の台北ビエンナーレだ。キュレーションを担当したのは徐⽂瑞(Manray Hsu)とヴァシフ・コルトゥン(Vasif Kortun)だった。このビエンナーレでは「新⾃由主義と資本主義のグローバル化から⽣じた問題の集合体」に取り組むことを明確な⽬的として掲げていた。ビエンナーレ⾃体は基本的には現代美術の展覧会に⾒せかけた抗議運動だったが、それにも関わらず予想外の事件が起きた。ビエンナーレが開幕した週末に、まさに美術館の⽬の前である台北の主要幹線道路の中⼭北路で、台湾市⺠が警察と⾎みどろの衝突をする激しい抗議暴動が起こったのだ。
さらに予想外だったのは、これらの抗議がビエンナーレの急進的な反グローバル化の作品や展⽰概要とは無関係だったことである。抗議運動に参加した台湾⼈はむしろ、中国政府の使節の到着、そして中国政府関係者の⾃動⾞の移動経路に台湾の国旗を掲揚しないといった中国の要求を台湾政府が受け⼊れたことに抗議したのである。台湾⼈は主権と⺠主主義の喪失を恐れていた。
さらに予想外だったのは、これらの抗議がビエンナーレの急進的な反グローバル化の作品や展⽰概要とは無関係だったことである。抗議運動に参加した台湾⼈はむしろ、中国政府の使節の到着、そして中国政府関係者の⾃動⾞の移動経路に台湾の国旗を掲揚しないといった中国の要求を台湾政府が受け⼊れたことに抗議したのである。台湾⼈は主権と⺠主主義の喪失を恐れていた。

Internacional Errorista, “We are all Errorists” (Taipei Biennial, 2008).
Courtesy of Internacional Errorista and Taipei Fine Arts Museum.
Courtesy of Internacional Errorista and Taipei Fine Arts Museum.
このビエンナーレに出展した海外のアーティスト達は、アーティストであると同時に、ロンドンからブエノスアイレスまで反グローバル化のデモに参加する社会活動家でもあったが、この断絶には愕然とした。彼らは地球規模の資本主義に抵抗する社会運動には、全世界で共通する何かがあるはずだと思い込んでいた。インターネットによって確実に接続された世界の繋がりを前提としていたのだ。ところが、本当のところはそれぞれの地域の運動はそれぞれ固有の問題を抱えていると、アーティスト達は気付くことになった。加えて、世界の繋がりは定かではない、ということにも。台湾、あるいは⾹港の⺠族⾃決運動は、近年バラバラになり始めているヨーロッパ⼤陸やイギリスでの抗議運動にどのように当てはめられるのだろうか。
ただ、アジアでビエンナーレ化現象が始まって25年を経て、何かしらの共通点は確実に形になり始めているはずだ。これまでの状況を⾒て⾔えるのは、アジアで組織的なモデルが強固になり、アジアの現代美術関係者のコミュニティーが出現したということだ。アートの専⾨家や運営者は今やビエンナーレに携わることをキャリアとし、⼀⽅では地元の⼈々と交流し、もう⼀⽅では国際的なネットワークを築いている。東アジアと東南アジアの様々なビエンナーレに参加すると、同じ顔ぶれに出会う。同じ⾯々の学芸員、アーティスト、学者、政府関係者、ギャラリスト、コレクター、アート・メディアなどであり、世界中を飛び回るアジアのアート関係者が誕⽣している。彼らはアジアのあらゆる国出⾝の国際協調主義者であり、国外移住者や欧⽶批評の⽀持者も含まれている。英語が彼らの共通⾔語である。
これはパラダイムとは⾔えないが、その始まりではある。共通点を⾒つけ出そうとする強い意思が継続的に顕れ、地域の共通点を模索する試みはますます強く⼤胆になってきている。
ただ、アジアでビエンナーレ化現象が始まって25年を経て、何かしらの共通点は確実に形になり始めているはずだ。これまでの状況を⾒て⾔えるのは、アジアで組織的なモデルが強固になり、アジアの現代美術関係者のコミュニティーが出現したということだ。アートの専⾨家や運営者は今やビエンナーレに携わることをキャリアとし、⼀⽅では地元の⼈々と交流し、もう⼀⽅では国際的なネットワークを築いている。東アジアと東南アジアの様々なビエンナーレに参加すると、同じ顔ぶれに出会う。同じ⾯々の学芸員、アーティスト、学者、政府関係者、ギャラリスト、コレクター、アート・メディアなどであり、世界中を飛び回るアジアのアート関係者が誕⽣している。彼らはアジアのあらゆる国出⾝の国際協調主義者であり、国外移住者や欧⽶批評の⽀持者も含まれている。英語が彼らの共通⾔語である。
これはパラダイムとは⾔えないが、その始まりではある。共通点を⾒つけ出そうとする強い意思が継続的に顕れ、地域の共通点を模索する試みはますます強く⼤胆になってきている。

Mali Wu, “Taipei Tomorrow As A Lake Again”, 2008,
Installation at 2008 Taipei Biennial.
Courtesy of Mali Wu and Taipei Fine Arts Museum.
これまでにない意欲的な試みの一つが、2017年に東京の森美術館で開催された「サンシャワー:東南アジアの現代美術展 1980年代から現在まで」*である。森美術館はアートの地域動向を率いる真のリーダーとして、近年急速にその存在感を増している。実際にアジア地域のリーダーとしての役割を積極的に引き受ける、アジアで数少ない美術館であり、単に地域の⼈々に奉仕する美術館とは対照的である。アジアの多くの国のアート関連施設は、⼀般的に2種類の任務を担っている。一つに、国の美術史を明らかにすることで国作りに貢献する役⽬がある。もう一つの任務は、施設内で欧⽶の巡回展を開催し、欧⽶の美術史と関連づけて⾃国の美術史を立証することである。
*「サンシャワー:東南アジアの現代美術展 1980年代から現在まで」は森美術館と国立新美術館の2館で同時開催された
だからといって、サンシャワー展が⼤成功だったとは⾔えない。展覧会では「多⺠族、多⾔語、多宗教の東南アジア地域ではダイナミックで多様な⽂化が育まれてきました」と、ある種の責任を放棄するような形で展⽰概要の紹介をし、展⽰されたアート作品は全体的に⾒ると⼀貫性に⽋けていた。それでも作品群から共通した特徴を⾒出すことはできる。南西アジア地域のアート作品では、地域⽂化の復興の必要性、すなわち、均質化されグローバル化された同質性の中で⼟着の⽂化的要素を再主張する必要性が共通している。また、暗い歴史や歴史的過ち、現在の不正を明らかにすることで、和解し社会を前進させたいという願望がある。これらの動きは国境によって制限されているが、少なくともアジアのアート界では相互に理解し評価し合おうという気運が⾼まってきている。
多様なアジアの⼈々が包括的な物語に合意するのはまだ不可能かもしれないが、現段階で実現可能で、より本質的で柔軟なのは、アーティストやキュレーター、批評家による地域ネットワークの形成である。近年アジアのアート関係者は、地域の美術館でのパネルディスカッションやグループ展など、⼤衆向けのビエンナーレ以外のイベントに定期的に互いを招待する機会を設けている。これまで以上にアジア間の交流や対話の機会が増えているのだ。
*「サンシャワー:東南アジアの現代美術展 1980年代から現在まで」は森美術館と国立新美術館の2館で同時開催された
だからといって、サンシャワー展が⼤成功だったとは⾔えない。展覧会では「多⺠族、多⾔語、多宗教の東南アジア地域ではダイナミックで多様な⽂化が育まれてきました」と、ある種の責任を放棄するような形で展⽰概要の紹介をし、展⽰されたアート作品は全体的に⾒ると⼀貫性に⽋けていた。それでも作品群から共通した特徴を⾒出すことはできる。南西アジア地域のアート作品では、地域⽂化の復興の必要性、すなわち、均質化されグローバル化された同質性の中で⼟着の⽂化的要素を再主張する必要性が共通している。また、暗い歴史や歴史的過ち、現在の不正を明らかにすることで、和解し社会を前進させたいという願望がある。これらの動きは国境によって制限されているが、少なくともアジアのアート界では相互に理解し評価し合おうという気運が⾼まってきている。
多様なアジアの⼈々が包括的な物語に合意するのはまだ不可能かもしれないが、現段階で実現可能で、より本質的で柔軟なのは、アーティストやキュレーター、批評家による地域ネットワークの形成である。近年アジアのアート関係者は、地域の美術館でのパネルディスカッションやグループ展など、⼤衆向けのビエンナーレ以外のイベントに定期的に互いを招待する機会を設けている。これまで以上にアジア間の交流や対話の機会が増えているのだ。

Installation view: SUNSHOWER: Contemporary Art from Southeast Asia 1980s to Now,
The National Art Center, Tokyo / Mori Art Museum, 2017.
Photo: Kioku Keizo. Photo courtesy: Mori Art Museum, Tokyo.
The National Art Center, Tokyo / Mori Art Museum, 2017.
Photo: Kioku Keizo. Photo courtesy: Mori Art Museum, Tokyo.
このネットワークの新たな交差点の一つが、2020年5⽉に台湾で創刊されたオンライン専⾨誌『キュレトグラフィー(Curatography**)』だ。中国語と英語で発⾏される同誌は、「現代アートとキュレーション⽂化の探求」、具体的には 「東アジアと東南アジアにおける⽂化⽣産の地政学的側⾯ 」に特化している。台湾⼈編集部の林宏璋(Hongjohn Lin)、徐⽂瑞(Manray Hsu)、羅秀芝(Sandy Lo)、張懿⽂(Yi-wen Chang)に加え、創刊2号では記事の寄稿者として、アイリーン・レガスピ・ラミーレス(Eileen Legaspi Ramirez・フィリピン)、ヨアン・ゴルメル(Yoann Gourmel・パリのパレ・ド・トーキョーのキュレーター)、ラクス・メディア・コレクティヴ(Raqs Media Collective・インド)、ルアングルパ(Ruangrupa・インドネシア)、パウィット・マハサリナン(Pawit Mahasarinand・タイのバンコク芸術⽂化センター元所長)が加わった。
** デーヴィッド・フレージャーは、キュレトグラフィー企画に携わり、プレス向けに同誌の英語資料を作成している
「キュレトグラフィー」は新造語であり、「キュレーションの製図や執筆」と定義できる。アジア地域のキュレーターやアーティストを⼀堂に集め、それぞれの個⼈的な経験を共有するという基本的な案から始まった。しかしこの考えは、ボリス・グロイス(Boris Groys)の「⽂化的記録(cultural archive)」の考えやジャック・ランシエール(Jacques Rancieres)の「政治的なもの(the political)」の概念を参照した学理的な⾒解に基づいている。ここで⽰唆されているのは、歴史と歴史的真実は常に偶発的なものであり、普遍的な価値からは遠ざかるべきであるということだ。グロイスに習うならば、私達にあるのは確実性ではなく、「時の経過に伴う安定という虚構」だ。
現在の『キュレトグラフィー』の関⼼事は、作品の芸術的または⾦銭的価値を判断する際に、作品自体の本質的な特性よりも、歴史的結果とも⾔える政治が判断基準において優先されるということだ。今の時代、誰が美学や美を語るだろうか。例えば、『キュレトグラフィー』の創刊号には、ヨアン・ゴルメルとエロディ・ロイエル(Elodie Royer)が執筆した「アメリカの花(Les fleures américaines)」という記事が掲載された。「アメリカの花」とは2012年にパリで開催された展覧会のタイトルであり、記事では展覧会と近代美術の政治史について以下のような論が展開される。1900〜1910年代のパリで、ガートルード・スタイン(Gertrude Stein)とその兄弟が熱⼼にピカソやマティスの作品を収集し、そのスタインの収集品が1929年に設⽴されたニューヨーク近代美術館(MoMA)の初期コレクションに⼤きな影響を与え、それが現在では⼀般的な近代美術史の執筆の基礎となっている。ゴルメルとロイエルはこれ以上の主張はしていないが、政治的成果が⽂化に価値を与えたという⾒解は、世界美術の物語における西洋美術の優位性といった、より⼤きな歴史的物語に異議を唱える際の基盤となりうるだろう。
** デーヴィッド・フレージャーは、キュレトグラフィー企画に携わり、プレス向けに同誌の英語資料を作成している
「キュレトグラフィー」は新造語であり、「キュレーションの製図や執筆」と定義できる。アジア地域のキュレーターやアーティストを⼀堂に集め、それぞれの個⼈的な経験を共有するという基本的な案から始まった。しかしこの考えは、ボリス・グロイス(Boris Groys)の「⽂化的記録(cultural archive)」の考えやジャック・ランシエール(Jacques Rancieres)の「政治的なもの(the political)」の概念を参照した学理的な⾒解に基づいている。ここで⽰唆されているのは、歴史と歴史的真実は常に偶発的なものであり、普遍的な価値からは遠ざかるべきであるということだ。グロイスに習うならば、私達にあるのは確実性ではなく、「時の経過に伴う安定という虚構」だ。
現在の『キュレトグラフィー』の関⼼事は、作品の芸術的または⾦銭的価値を判断する際に、作品自体の本質的な特性よりも、歴史的結果とも⾔える政治が判断基準において優先されるということだ。今の時代、誰が美学や美を語るだろうか。例えば、『キュレトグラフィー』の創刊号には、ヨアン・ゴルメルとエロディ・ロイエル(Elodie Royer)が執筆した「アメリカの花(Les fleures américaines)」という記事が掲載された。「アメリカの花」とは2012年にパリで開催された展覧会のタイトルであり、記事では展覧会と近代美術の政治史について以下のような論が展開される。1900〜1910年代のパリで、ガートルード・スタイン(Gertrude Stein)とその兄弟が熱⼼にピカソやマティスの作品を収集し、そのスタインの収集品が1929年に設⽴されたニューヨーク近代美術館(MoMA)の初期コレクションに⼤きな影響を与え、それが現在では⼀般的な近代美術史の執筆の基礎となっている。ゴルメルとロイエルはこれ以上の主張はしていないが、政治的成果が⽂化に価値を与えたという⾒解は、世界美術の物語における西洋美術の優位性といった、より⼤きな歴史的物語に異議を唱える際の基盤となりうるだろう。

Hoy Cheong Wong, “Maid in Malaysia”, 2008.
Courtesy of Hoy Cheong Wong and Taipei Fine Arts Museum.
『キュレトグラフィー』の創刊号では他にも、フィリピンの学者、アイリーン・レガスピ・ラミーレスが「空⽩の候補者名簿はない(There are No Blank Slates)」と題した記事を寄稿している。記事の中でラミーレスは、アジア諸国が歴史的重荷にいまだに苦しんでいることを嘆く。また、アジアの芸術運動を類型化する⾏為が独裁主義体制や⼈権のようなより根本的な問題を矮⼩化していると指摘する。「ポストコロニアルの場所の多くがそうであるように、アジアは常に台頭の⽐喩と結び付けられてきた。特に現代アートに関してその傾向はなおさら強い」ラミーレスは続けて語りかける。「美術史は微妙な地域差に無頓着である」。
ロドリゴ・ドゥテルテ(Duterte)が統治するフィリピンにおける現代美術の問題は、⽇本や韓国、ベトナムでどのようにして意義あるものになるだろうか。この問題には具体的に、貧困、警察による死刑執⾏、混乱を極める植⺠地時代の歴史、主要な国家収⼊となっている⾃国の⼈々の輸出が含まれる。これは⾮常に難しい問いである。冒頭で述べたように、アジアのパラダイムというものはまだ存在しない。そして、そのような「普遍的」な活動はおそらく今後も必要とされないだろう。しかし、アジア間の対話の継続やネットワーク形成、さらに友情は、これから⼤きな励みになるはずだ。少なくとも、アジアの地域に住む私達は皆、互いに話し合う⽅法を学んでいる最中である。
ロドリゴ・ドゥテルテ(Duterte)が統治するフィリピンにおける現代美術の問題は、⽇本や韓国、ベトナムでどのようにして意義あるものになるだろうか。この問題には具体的に、貧困、警察による死刑執⾏、混乱を極める植⺠地時代の歴史、主要な国家収⼊となっている⾃国の⼈々の輸出が含まれる。これは⾮常に難しい問いである。冒頭で述べたように、アジアのパラダイムというものはまだ存在しない。そして、そのような「普遍的」な活動はおそらく今後も必要とされないだろう。しかし、アジア間の対話の継続やネットワーク形成、さらに友情は、これから⼤きな励みになるはずだ。少なくとも、アジアの地域に住む私達は皆、互いに話し合う⽅法を学んでいる最中である。