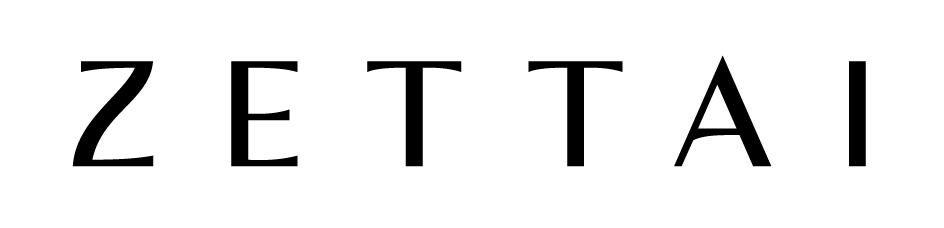*閲覧注意(本記事はヴィーガンの方にとって不快な内容を含む可能性があります)
豚に対する世評はひどいものだ。例えば、旧約聖書では豚は不浄な動物とされている。豚にまつわる説話のうち、特によく知られているのは、新約聖書の『マタイによる福音書』にある次のようなエピソードだ。人間の身体から追い出された悪霊たちは、代わりとなる肉体を求め、近くにいた罪のない豚の群れを新たな宿主とする。その直後、悪霊たちは崖を下って湖になだれ込み、哀れな豚たちの短い命を終わらせてしまう。汚い部屋は豚小屋に例えられるし、人がガツガツと食事する様子は「豚のような食べ方」と表現される。実際のところ、豚は健康的で整った小屋に暮らす清潔な動物であるだけでなく、豚として豚のように際限なく食べるよう生まれついているのだ(神の御心のままに!)しかし、豚たちが耐えているいわれのない侮辱の最たるものは、彼らの名前が権力におもねる人々を蔑む言葉として使われていることかもしれない。
パフォーマンス
豚とその友
カリソライテ・ウヒラ
英文: レアファー・ウィルソン aka オルガ・クラウズ (Leafa Wilson, aka Olga Krause)
和訳:津川 万里 (Mari Tsugawa)

Kalisolaite ‘Uhila, “Pigs in the Yard”, 2011,
documentation of performance,
Aotea Square Performance Arcade, Auckland

Artist unknown, “The Miracle of the Gadarene Swine”,
circa 1000, tempera colors, gold leaf, and ink on parchment,
digital image courtesy of the Getty's Open Content Program.
これらの物語や表現はどれも、この美しく知的で高い感性を持つ動物が本来受けるべき評価からは程遠い。ほとんどの場合、豚は人間の食糧となり、私たちが当然のように享受しているゼラチン、ベルト、ジャケット、スーツといった多岐にわたる製品を提供する運命をたどる。悲しい事実だが、オーガニック牧場やSPCA(動物虐待防止協会)の認証を受けた牧場以外では、大抵の豚は営利中心の集約的な畜産環境で短い生涯を過ごす。彼らが詰め込まれる小屋には食べる場所、寝る場所、排せつする場所を分けるスペースすらないため、豚たちは病気や苦痛にさらされている。しかし、こうした理解は、パフォーマンス・アーティスト、カリソライテ・ウヒラの「Pigs in the Yard (囲いの中の豚)」と題された強烈な作品に無効化される。この作品によって、ウヒラが家族とともにトンガ人コミュニティーのメンバーとして暮らすアオテアロア(ニュージーランド)で数回上演された。


Kalisolaite ‘Uhila, “Pigs in the Yard”, 2011,
documentation of performance, Aotea Square
Performance Arcade, Auckland,
photos by Linda Trubridge and Sam Trubridge.
オセアニアの全域で、豚は神聖な生き物。トンガ社会では、豚は裕福さと社会階層の流動性を象徴することから、深い敬意を持って扱われてきた。たくさんの豚を持つものは、それを差し出すことによってトンガの貴族や王族の輪に加わることができる。また、豚は祝日や婚礼、葬儀、誕生日といった特別な日の供物や贈り物にもなる。トンガの伝統では子供の1歳の誕生日は重要な節目とされている。毎年6月4日、トンガ王国は1970年に大英帝国から解放された記念日を祝う。この国の憲法記念日は11月4日だが、一年でもっとも盛り上がる祝日は現国家君主の誕生日だ(現在はトゥポウトア・ウルカララ皇太子)。ウヒラは、貧富を問わず誰もが祭事に敬意を表して自分の豚を捧げるこれらの祝祭について語る。豚は一種の通貨であり、文化資本なのである。
トンガ人の視点を通すと、豚に対する完全に異なった理解と扱いが浮かび上がってくる。インドの神聖な牛たちのように自由にあたりをうろつくトンガの豚たちは、統べるものと統べられるものを結ぶ暗黙の役割を果たしている。ウヒラの作品は、その場を豚と人間が一つの小屋を共有し、互いに敬意を払い平等に存在する空間に変えることで、豚を西洋的な豚小屋の概念から解放する。
トンガ人の視点を通すと、豚に対する完全に異なった理解と扱いが浮かび上がってくる。インドの神聖な牛たちのように自由にあたりをうろつくトンガの豚たちは、統べるものと統べられるものを結ぶ暗黙の役割を果たしている。ウヒラの作品は、その場を豚と人間が一つの小屋を共有し、互いに敬意を払い平等に存在する空間に変えることで、豚を西洋的な豚小屋の概念から解放する。

Tongan pigs and laundry, 2016,
photo by Wm Adams (billtrips.com).
photo by Wm Adams (billtrips.com).
ウヒラは、豚はトンガの文化と密接に関連していると言う。豚の命は宮廷の供物として、あるいは家族の祝い事のごちそうとして絶たれるにも関わらず、ウヒラは豚に(ウヒラによると神聖かつ政治的である)人間的な役割を見出す。東南アジアの非イスラム圏の食文化でよく見られるように、豚はあらゆる部位を活用されることでその犠牲を尊ばれる。耳や鼻、腸、足にいたるまで、この動物には食べられない部位はないと考えられており、その死は決して無駄にされない。豚はその全てが生存の糧なのである。オセアニアの島々でも豚は同様に扱われるが、その理由は少し異なる。この地域の人々にとって、豚は「超自然的な」食べ物であり、供物なのだ。
「Pigs in the Yard」にも、豚にまつわるトンガの儀式に特有の要素が作品のあちこちに散りばめられている。まず、ウヒラが小屋を共有する相手は子豚である。この豚は大きすぎたり太りすぎたりしておらず、したがってトンガのしきたりに照らしても一緒に暮らすことに問題はない。抱えて運べないほど大きな豚はタープ(神聖)とされ、庶民は飼うことが許されていない。トンガ王国の島々の外で上演されたこの作品は、一般的な豚の生活についての大胆なステートメントとなった。
「Pigs in the Yard」が2011年初頭にサウス・オークランドのマーンガレ・アーツ・センターで初めて上演されたとき、ウヒラは来場者とともに囲いに入り、会場の中庭に豚の群れを放って、豚たちがトンガにいたならば享受していたかもしれない自由を体験させた。その場をあたかもトンガのフォヌア(地)であるかのように扱ったこのパフォーマンスは、「神聖なホワイト・キューブ」にとらわれないアートの展示空間のあり方を明示したパワフルで常識破りのステートメントだった。
「Pigs in the Yard」にも、豚にまつわるトンガの儀式に特有の要素が作品のあちこちに散りばめられている。まず、ウヒラが小屋を共有する相手は子豚である。この豚は大きすぎたり太りすぎたりしておらず、したがってトンガのしきたりに照らしても一緒に暮らすことに問題はない。抱えて運べないほど大きな豚はタープ(神聖)とされ、庶民は飼うことが許されていない。トンガ王国の島々の外で上演されたこの作品は、一般的な豚の生活についての大胆なステートメントとなった。
「Pigs in the Yard」が2011年初頭にサウス・オークランドのマーンガレ・アーツ・センターで初めて上演されたとき、ウヒラは来場者とともに囲いに入り、会場の中庭に豚の群れを放って、豚たちがトンガにいたならば享受していたかもしれない自由を体験させた。その場をあたかもトンガのフォヌア(地)であるかのように扱ったこのパフォーマンスは、「神聖なホワイト・キューブ」にとらわれないアートの展示空間のあり方を明示したパワフルで常識破りのステートメントだった。

本作品の2回目の上演は、オークランドのダウンタウン中心部にあるアオテア・スクエアで開催された2011パフォーマンス・アーケードの一部として行われた。ウヒラは空の貨物コンテナを彼自身と一匹の小さな豚が仲良く暮らす小屋につくり変えた。このパフォーマンスで、ウヒラは豚の生活のあらゆる側面を取り上げた。ジョージ・オーウェルの『動物農場』の言葉を借りれば、「彼らは豚と人間を見比べたが、どちらが豚でどちらが人間なのか見分けがつかなかった」。ウヒラは人間が豚より重要な存在ではないことを表現している、と解釈することもできる。ただし、トンガ的な感覚では、ウヒラは自身を豚の暮らしまでおとしめているのではない。どちらかというと、彼のほうが豚とともに過ごす栄誉にあずかっているのだ。この場面において、豚はウヒラの作品にとって最も重要な存在なのである。
「Pigs in the Yard」では、ウヒラは黒いラバーラバという衣服といくつかのパンダナスという装具のみを身に着けている。これはトンガの典型的な伝統的な装いだ。農家の庭の様子を模し、そこで過ごす人間と豚に快適さと安全とスペースを与えるため、貨物コンテナの床には黒いポリエチレンが張られ、その上に厚くわらが敷かれた。二者はそれぞれ自分の水入れを持っており、一枚の麻布の上で兄弟のように一緒に眠った。意図的にトンガの牧歌的な雰囲気をアオテアロア最大の都市に持ち込んだ「Pigs in the Yard」は、同種の作品ではおそらく初めて田舎の畜産現場の文脈の外側で上演されたオンサイトのエンデュアランス・アート作品だ。
「Pigs in the Yard」では、ウヒラは黒いラバーラバという衣服といくつかのパンダナスという装具のみを身に着けている。これはトンガの典型的な伝統的な装いだ。農家の庭の様子を模し、そこで過ごす人間と豚に快適さと安全とスペースを与えるため、貨物コンテナの床には黒いポリエチレンが張られ、その上に厚くわらが敷かれた。二者はそれぞれ自分の水入れを持っており、一枚の麻布の上で兄弟のように一緒に眠った。意図的にトンガの牧歌的な雰囲気をアオテアロア最大の都市に持ち込んだ「Pigs in the Yard」は、同種の作品ではおそらく初めて田舎の畜産現場の文脈の外側で上演されたオンサイトのエンデュアランス・アート作品だ。

Kalisolaite ‘Uhila, “Pigs in the Yard”, 2011,
documentation of performance,
Aotea Square Performance Arcade, Auckland,
photo by Linda Trubridge and Sam Trubridge.
農場といえば、Specialist Pig Practiceというウェブサイトによると、豚の状態はその豚がどのような姿勢で寝ているかで判断できるという。寝るときに胴体の下に脚を隠しているなら寒いと感じており、脚を伸ばしているなら快適である、という具合に。群れの中で地位の低い豚たちは重なりあって眠り、より地位の高い個体は密集を避けて寝る。また、「Pigs in the Yard」の2回目のパフォーマンスに出演した豚は、まだ成長途中の子豚だった。人間の赤ん坊と同じように、この子豚もたくさんの睡眠を必要とした。ウヒラと豚が隣り合わせで寝ている写真は、彼らが豚のヒエラルキーにおいて同等であり、相互依存関係にあることを示している。
「Pigs in the Yard」を上演するにあたり、祖国の神聖な生贄となる動物に敬意を表するため、ウヒラは自身の夫や父、息子、孫息子、伯父、友人としての役割から距離を置く。慣れ親しんだ環境の安楽に背を向け、トンガの伝統文化におけるマーナ(霊的な力と地位)を人知れず支える政治的な存在としてこの動物を記念することによって、ウヒラは豚をハイ・アートに昇華させているのである。
「Pigs in the Yard」オンサイト・パフォーマンス(2011年)。アオテアロア(ニュージーランド)、オークランドのアオテア・スクエアで開催された「パフォーマンス・アーケード」にて。
「Pigs in the Yard」を上演するにあたり、祖国の神聖な生贄となる動物に敬意を表するため、ウヒラは自身の夫や父、息子、孫息子、伯父、友人としての役割から距離を置く。慣れ親しんだ環境の安楽に背を向け、トンガの伝統文化におけるマーナ(霊的な力と地位)を人知れず支える政治的な存在としてこの動物を記念することによって、ウヒラは豚をハイ・アートに昇華させているのである。
「Pigs in the Yard」オンサイト・パフォーマンス(2011年)。アオテアロア(ニュージーランド)、オークランドのアオテア・スクエアで開催された「パフォーマンス・アーケード」にて。

Kalisolaite ‘Uhila, “Pigs in the Yard”, 2011, documentation of performance,
Aotea Square Performance Arcade, Auckland.
Aotea Square Performance Arcade, Auckland.